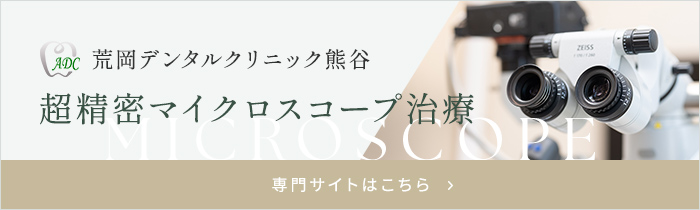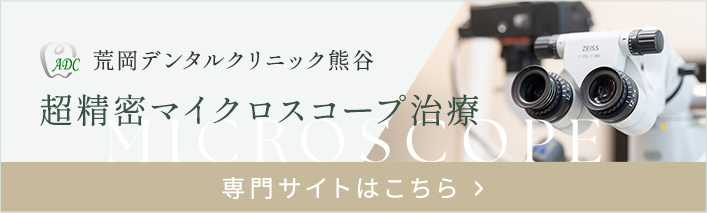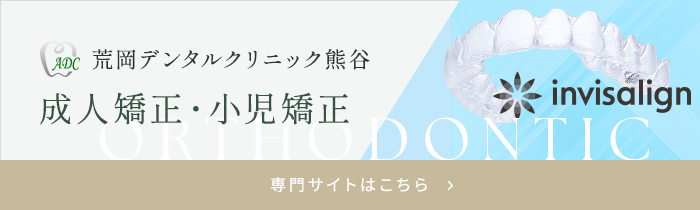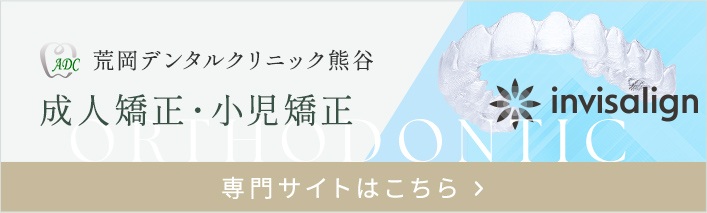こんにちは!
先日の日食、台湾の友人の歯医者さんが台湾で撮った金環日食の写真を送ってくれました。
きれいですね!
日本で次に金環日食が観れるのは2030年だそうです。
さて、昨日は矯正診療日でした。
朝からたくさんの方が治療や相談にお見えになっていました。
やっぱり、綺麗な歯並びは素敵ですよね。
見た目はもちろん、かみ合わせの改善や顎関節への負担の軽減など得られる効果は大きいと思います。
しかしそもそもなぜ元から歯並びが綺麗な人と乱れている人がいるのでしょうか?
今日は、少し詳しく歯並びが悪くなる原因をお話ししたいと思います。
まず、矯正治療で対象としているのは、歯と顎(あご)です。
歯並びが悪くなるのは、自分の生えてきた歯と自分の歯が生えるスペース(顎)が不調和を起こしているからです。
要は、自分の顎が小さかったら、歯がちょうどいい大きさならまっすぐ並ぶけど、大きな歯が生えてきたら窮屈で生える場所がなくガタガタに並んでしまいます。
逆に、自分の顎が大きくて、それに対して歯が小さければ、すきっ歯になります。
自分は出っ歯だ!と一口に言っても、上顎が出ていて出っ歯になっている人もいれば、
顎の関係は問題ないが、歯が前に飛び出していて出っ歯になっている人もいます。
なので、検査と診断を行い、その人に合った治療をする必要があるのです。
そのための検査についてもまたお話の機会を持ちたいと思います。
また、以前にお話ししたこともありますが、何か癖があって歯並びが悪くなることもあります。
例えば、子供の頃指しゃぶりをずっとしていただとか、いつも爪や鉛筆を噛んでいた、唇をなめたり噛んだりしていた、口呼吸でいつも口が開いていた などです。
どうしてこれで歯並びが悪くなるのでしょうか?
それは筋肉にあります。
口の周りには唇の周りをぐるっと囲む口輪筋という筋肉が付いています。
そもそも、歯というのは常に動くものなのです。
なので、歯を1本抜いて奥の隣の歯が倒れてしまっただとか、下の歯を抜いて放置していたら上の対合する歯が伸びてきたということになるのです。
しかしだからこそ矯正治療で歯を動かして歯並びを治すことができるのです。
話を戻すと、その口輪筋が口を開けていると働かないし、逆に吸ったりしていると常に力をかけていることになります。
歯列は、舌や口輪筋などの筋肉の中立帯に並んでおり、そのバランスが崩れると力に押されて動いてしまうのです。
なので、口輪筋が適正に働いていないとその力で歯の前への移動が起こります。
出っ歯の原因になってしまうこともあります。
また、舌を歯に挟んで喋る癖があると、前歯が噛んでも接触しない開咬という状態になります。
幼少期の癖は、歯だけでなく顎の成長自体にも影響することがあります。
子供も大人も気をつけましょう。
次回の矯正診療日は7月12日日曜日です。
ご相談がある場合はご連絡ください。
荒岡デンタルクリニック 熊谷
荒岡 千尋